住宅ローンの変動金利を選ぶ割合
| 年度 | 割合 |
| 平成26年 | 52.5% |
| 平成27年 | 56.5% |
| 平成28年 | 50.2% |
| 平成29年 | 50.7% |
| 平成30年 | 60.5% |
変動金利の仕組み
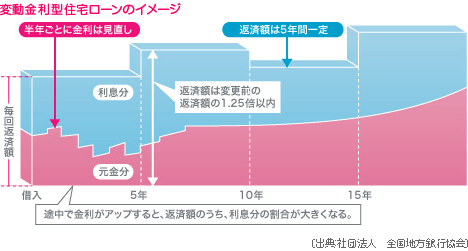
変動金利型とは5年間は返済額が変わらない住宅ローンです。
変わらないのは返済額で、金利は年に2回見直されます。
年に2回金利が見直されるのに、返済額が変わらないということは、同じ返済額の中で、利息に充当される割合と元金に充当される割合が月によって変わります。
(例)毎月8万円返済
- 4月は元金4万円、利息4万円
- 10月は元金3.5万円、利息4.5万円
変動金利の注意点
金利の上昇で元金の返済割合が減る
金利が上がれば、返済額は変わらないものの、利息に充当される額が増える分、元金に充当される額が減ってしまいます。
そうすると、実際は利息のみを支払っていることになり、元金は一向に少なくならないというリスクがあることを忘れると危険です。
金利の上昇で支払額が増える
変動金利型は、5年経過して返済額を再計算する際に、新返済額はもとの返済額1.25倍までというルールがあることが一般的です(担当者にご確認ください)。
したがって、金利が上がっても返済額は1.25倍までしか上昇しないため、返済額自体の負担は大きくありません。
金利の上昇で未払い利息のリスクが高まる
金利上昇による支払額の増加は上で述べたとおりですが、ここからが注意点です。
返済額には元の返済額の1.25倍という上限設定があっても、利息額には上限がありませんので、急激に金利が上昇した場合には、支払うべき利息が返済額を超えて、未払い利息が発生する危険性があります。
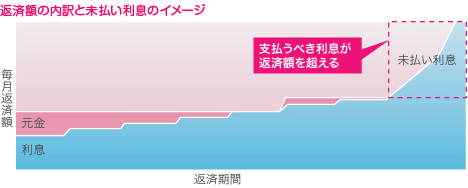
(例)金利が5年間で8倍に上がり、返済額は1.25倍に上がったケースを想定します。
- 0.5% 返済額8万円(元金3万円、利息5万円)
- 4% 返済額10万円(元金0円、利息12万円)
※返済額の内訳は実際とは異なります。イメージを掴むためのものです。
上は極端な例ですが、未払い利息が生じると毎月の返済額を超えてしまうため、生活に大きな支障来すことになります。
金利が下がらない理由
これは複数の金利を理解する必要があります。
実際に借入時に適用される金利は融資金利(=適用金利)と呼び、この融資金利は次の計算式によって導かれます。
- 基準金利2.475%ー優遇金利2%=融資金利0.475%
- 基準金利2.475%ー優遇金利1.75%=融資金利0.725%
上記①と②では優遇金利に幅があります。
このように借入時の優遇金利の引下げ幅が違えば、融資金利が変わります。
新規借入時や借換え時にのみ優遇金利が適用されるものなので、既に融資を受けて返済中の人には何の影響もありません。
したがって、変動金利型で既に融資を受けた方は、融資先の銀行のホームページを見て、ご自身が融資を受けたときの金利よりも随分引き下げられていたとしても、銀行が新規顧客獲得のために優遇金利を調整しているだけで、ご自身の変動金利が借入時よりも下がることはないのです。
終わりに
変動金利も上手に使えばメリットは大きいです。
金利上昇リスクに備えるために10年後に繰り上げ返済を行うとか、借り換えをするなどの方法もあります。
固定金利型とどっちが良いか悩むことも多いと思いますが、メリットで考えるよりも、それぞれのデメリットを天秤にかけてどちらのデメリットを許容できるかで選ぶと後悔は少なくなると思います。
特にアメリカに影響を受けて、日銀が政策金利の引き上げを実施する場合は、変動金利にも影響があるため、その動向と金利の引き上げが実施された場合の備え(家計の見直し)をしておく必要がありそうです。
- 1
- 2



