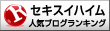年末調整
そもそも会社員で確定申告をする機会はそれほど多くないと思います。
というのも、勤務先である会社が社員に代わって税金を給与から予定収入に応じた概算額で毎月税金を納めているため、年末に行う「年末調整」によって過不足が調整されます。
この年末調整があるために会社員は確定申告をしなくて済んでいるのですが、例えば、入院して医療が嵩んだり、寄付をしたり、家を建てた場合には、年末調整とは別に還付申告を行うことで、一度は納付した税金から還付を受けることができるのです。
家を建てると確定申告をするのはなぜ?
住宅ローンを組むと必ず金利(利息)を元本とは別に支払う必要があります。
固定型でも変動型でも数%の金利を10~35年に渡って支払いますので、その金利だけでも数百~1000万円近くに上ることがあります。
そこで、住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借りて住宅を取得する場合に、金利負担の軽減を図るための制度で、取得者が納めた所得税の還付や住民税の控除を行うことで、税負担を軽くして住宅購入の後押ししようという国の施策が背景にあります。
そして、確定申告は、納付すべき所得税額を確定する一方で、所得控除制度や税額控除の金額、源泉徴収税額や税率によって、
本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる「還付申告」を用意しています。
住宅ローンを減税によって、納めた所得税を還付、住民税を控除してもらうためには、この「還付申告」が必要になるため、年末調整とは別に確定(還付)申告を行うのです。
なお、確定申告を行うのは初年度のみで、2年目以降は勤務先の年末調整で処理してもらえます。
税務署から確定申告後に「住宅借入金等特別控除申告書」が送付されますので、銀行から送付される借入金の年末残高等証明書を基に所定の事項を記入して、年末調整の時期に勤務先に提出しましょう。
住宅ローン減税は、所得税を算出した後で、税額から直接差し引く「税額控除」という仕組みをとっていますので、戻ってくる税額が分かりやすく(「ローン残高の1%」)、金額も大きいためにマイホームを検討中の方にはインパクト感があります。
しかし、それはハウスメーカーの営業マンにとっても同じで、お客さんを引き寄せる魅力ある殺し文句として利用されているのです。
所得税・住民税の控除額
| 適用期間 | 平成26年4月~令和3年12月31日まで |
| 控除上限額 | 借入金年末残高の1%
(上限4,000万円) ※認定長期優良住宅等は 上限額5,000万円 |
| 控除期間 | 10年 |
| 住民税の控除上限額 | 前年課税所得×7%
(上限136,500円) |
| 主な要件 |
①床面積が50m2以上
②借入金の償還期間が10年以上 |
なお、現行の消費税8%から10%の引き上げにより、住宅ローン減税の拡充政策が取られます。
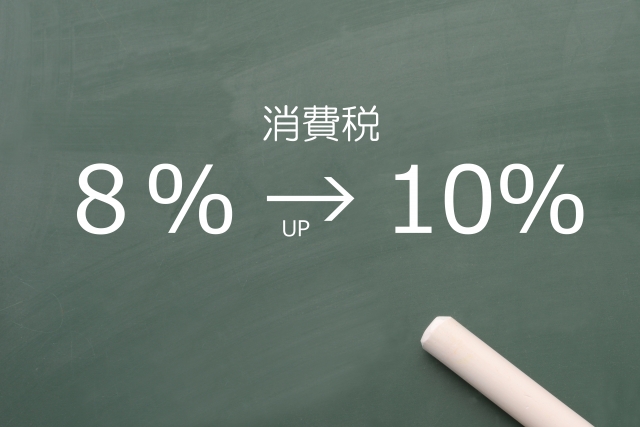
対象者は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合です。
拡充政策として、控除期間が10年から13年に延長されます。
また、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、次のいずれか小さい額です。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
(長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円)
住宅ローン控除と住民税
会社員の場合、給与から源泉徴収され納付した所得税が住宅ローンの借入年末残高の1%より低い額(所得税額から控除しきれない額)の場合は、個人住民税額から控除されますので安心してください。
なお、消費増税の拡張政策の住民税控除も同様です。
次のAさんの場合を例にとって解説します。

Aさんが2019年に納めた所得税20万円、翌年6月以降の住民税25万円(予定) 、年末ローン残高2800万円の場合をサンプルとします。
①住宅ローン減税額:年末ローン残高2800万円×1%により、28万円が上限額
②所得税:納めた所得税20万円から28万円が控除され、20万円が還付(8万円が控除しきれない)
③住民税:2020年6月以降に納付予定の住民税25万円から上記②の控除しきれなかった8万円が住民税から控除され、17万円に減額
結果28万円の節税効果がありました。
還付金が思ったより少ない原因
上の例を見るとお分かりのように、確定申告の手続によって、所得税は現金還付されます。
住民税は納める予定の額が減る(控除)されることになりますので、実際に手にする還付金は所得税分のみということになります。
住民税も所得税と同じように現金が還付されない点に注意が必要です。
加えて、ご自身が納付した額以上の税金は戻ってきませんので、営業社員の「家を建てると400万円が戻ってくる」という言葉を額面通りに受け取らないようにしましょう。
これが冒頭にお話しした「聞いていた金額より少ない。思ったより少ない」原因であり、営業社員の仕掛けた罠の正体です。
つまり、給与所得控除に社会保険料控除、基礎控除に扶養控除を合算していくと、年収800万円程度の場合でも所得は400万~500万円程度にまで下がりますし、年収600万円でも所得は300万円程度にまでなります。
子どもの数や扶養親族の状況によって所得は圧縮されますので、年収が一見高くても納める所得税も少なくて済むのです。
そうすると、所得税の納付額が少ないために住宅ローン控除によって還付される金額も少なくなるのです。
特に住宅ローンの借入額が3000万円より少ない場合には控除上限額400万円(長期優良認定住宅は500万円)には住民税控除分を考慮しても届かないということになります。
上限額の控除を受けるには、当然ながらローン残高が10年間4000万円を超えていて(利率や返済期間の状況によっても変わりますが、借入額は6000万円を超えている必要があり)、かつ、年間の所得税と住民税合計40万円を超えていなければなりません。
例えば、年収820万円(額面収入)の会社員で、配偶者は専業主婦、16歳未満の子どもが3人いる場合(生命保険料控除や個人型拠出型年金の所得控除等あり)の所得税の源泉徴収額は約33万円です。
この場合、住宅ローン借入額の年末残高が3300万円以上あれば納めた所得税は全額還付されるものの、住民税の控除を受けることはできません。
また、控除を受けることのできる期間は残り9年間ですから、年々ローン残高は少なくなっていきますので、借入額が少ない場合には、利息の支払いが少なくて済む代わりに、節税効果もそこまで期待できないのです。
なお、セキスイハイムの新築は、長期優良住宅建築等計画の認定を受けられますので、住宅ローンの借入額にもよりますが、10年間で最大500万円の減税の恩恵を受けることができます。
したがって、上述したとおり、捕らぬ狸の皮算用ではありますが、頭金(自己資金)の支出と住宅ローンの利息及び住宅ローン減税による節税効果のバランスを図りながら最適な資金計画を立てることをお勧めします。
確定申告の方法
住宅ローン控除の手続のみであれば、さほど難しくはありません。
国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」というサイトがあり、画面の指示にしたがって直接入力することでそのまま申告書を作成することもできます。
勤務先から交付された源泉徴収票と銀行から送付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、不動産登記事項証明書、工事請負契約書等を手元に置いて、記載された事項を入力していくと30分もあれば完成します。
しかし、不慣れでパソコン操作が苦手、尋ねながら手続をしたいという方は、できるだけ早めに申告書を入手した上で税務署を訪問し、書き方について細かくアドバイスを受けるとよいでしょう。
提出方法は、税務署に出向いて提出するほかに、e-Taxというすべてオンラインで提出する方法、郵送で行う方法があります。
出向くことが一番確実なのですが、確定申告時期は非常に混みますので、待ち時間が長いというのが難点です。
確定申告に必要な書類
住宅借入金等特別控除手続の際に提出する必要書類は以下のとおりです。
上記1の書類は銀行から毎年11~12月ころに送付されます。
上記2~6はセキスイハイムから家の引き渡しとともに交付されます。
確定申告の手続について不明な点は遠慮なく営業担当や管理担当に尋ねてください。きちんと手続をして減税の恩恵を受けましょう。
確定申告書の書き方は?
確定申告の書き方の見本は住宅支援機構のフラット35にリンクを貼っていますので参考にしてください。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
- 確定申告書A(第一表)の書き方
- 確定申告書A(第二表)の書き方
受取口座はネット銀行も利用可
還付金を受け取る振込口座はネット銀行でも可能です。
楽天銀行、住信SBIネット銀行などのネット銀行は国税の受取口座として指定することができますが、対応していないネット銀行もありますので、各金融機関のホームページでご確認ください。
振込までの期間は、約1ヶ月と考えておけば良いです。筆者の場合は、郵送して1ヶ月以内に指定した銀行に振り込まれました。
施主 住宅ローンを申し込む際に夫婦の収入合算を提案されたけどどうなの?似たような制度でペアローンもあるけどよく分からない。 こういった疑問にお答えします。 共働き世帯がマイホームを建てる・購入する際に住宅ローンをど[…]
10年固定金利タイプの住宅ローンとは、返済開始当初から10年間は金利が変わらない仕組みの住宅ローンのことです。「当初10年固定」という呼び方もあります。 この10年固定金利タイプは、住宅ローンの中でも比較的低い水準の金利で10年間、金[…]
家づくりのヒントになる面白いブログがいっぱいあります。
- 1
- 2